 |
| (日本歯科医師会HP:歯とお口のホームページより抜粋) |
 |
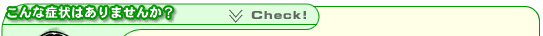 |
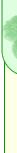 |
 |
| 1. 歯肉が赤くなっている。 |
| 2. 歯と歯の間の歯肉が、丸く厚みを持ってふくらんでいる。 |
| 3. 歯肉が腫れてぶよぶよしている。 |
| 4. 歯肉がむずがゆく、歯が浮いてる感じがする。 |
| 5. 歯みがきなどの軽い刺激で歯肉から血が出る。 |
| 6. 歯肉が赤紫になっている。 |
| 7. 歯肉が退縮し、歯が長く見える。 |
| 8. 口臭がつよくなった気がする。 |
| 9. 歯と歯の間に食べ物がはさまりやすい。 |
| 10. なにもしないのに歯肉から出血することがある。 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
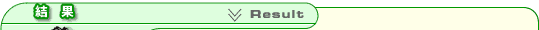 |
 |
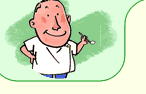 |
| ・ |
1〜5に当てはる項目があった人は歯肉炎の疑いがあります。 |
| ・ |
6〜10に当てはる項目があった人は歯周炎の疑いがあります。 |
|
 |
|
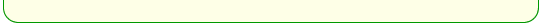 |
|

| ◆健康な歯肉 |
| 歯肉の色は薄いピンクで、歯と歯の間にまでしっかり入り込んでいます。また、触ると弾力があり引き締まっていて、軽い刺激などでは出血しません。 |
 |
|

| ◆歯肉炎とは |
| 歯肉に炎症が起きた状態です。歯と歯肉の境目に付いたプラーク中の細菌が毒素を出し、炎症を引き起こします。歯肉は赤く腫れ、そのため歯の周りに歯周ポケット(仮性ポケット)と呼ばれる溝ができ、プラークがますますたまりやすくなります。 |
 |
|

| ◆歯周炎とは |
| 炎症が歯を支えている骨にまで進んだ状態です。歯肉炎によってできた歯周ポケット(仮性ポケット)は深くなり真性ポケットになります。そこにたまったプラーク中の細菌は毒素が強く、歯周病を進行させ歯を支える骨(歯槽骨)まで溶かします。 |
 |
|
 |
| |
 |
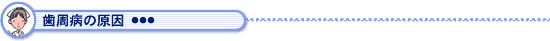 |
 |
| 局所的要素 |
| 1. プラーク(歯垢) |
細菌の塊であるプラークが歯と歯肉の境目につき炎症をひきおこします。 |
| 2. 歯石 |
プラークに唾液中のカルシウムなどが沈着し歯石になります。歯石は歯肉を刺激し、炎症を更に悪化させます。 |
| 3. 不正咬合 |
歯並びが悪い部分は歯みがきが不十分になり、プラークがたまり、炎症がおこりやすくなります。
また、かみ合せが悪いと、一部の歯に過度の負担がかかり歯周組織をいためる原因にもなります。 |
| 4. 歯に合わなくなった冠、詰物など |
歯に合わなくなった冠、詰め物などは歯肉を傷つけ炎症を起こします。 |
| 5. 良習慣 |
(1)
口呼吸・・・口の中が乾燥し、プラークが付着しやすくなり、また、歯肉の抵抗力も弱まります。
(2) 歯ぎしり・・・歯は、歯ぎしりのような横からの力に弱いため、歯周組織に負担がかかります。 |
|
|
 |
| 全身的要素 |
| 1. 内科的疾患(糖尿病、高血圧など) |
| 2. 喫煙 |
| 3. 栄養の偏った食事 |
| 4.
ホルモンバランスの不安定 |
| 5. 血液疾患 |
| 6. 精神的ストレス |
| 7. カルシウム拮抗剤(ニフェジピン)や抗てんかん剤(フェニトイン)などの薬。 |
|
|
 |
 |
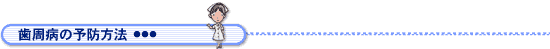 |
 |
|
 |
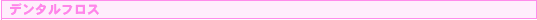 |
 |
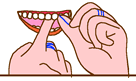 |
歯と歯の間の汚れをとります。
歯肉を傷つけないようにゆっくり前後に動かしながら挿入し、歯の側面をこすりながら左右に2〜3回動かします。 |
|
 |
|
|
 |
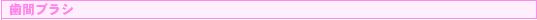 |
 |
歯と歯のすき間が広い場合に使います。
歯肉を傷つけないようにゆっくり挿入し、前後に2〜3回動かし汚れをとります。 |
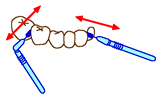 |
|
 |
|
|
 |
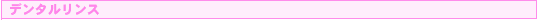 |
 |
就寝中は、唾液の量が少なく、歯周病の原因となる細菌が繁殖しやすくなります。
就寝前にデンタルリンスを使うと、細菌の抑制に効果があります。 |
|
 |
|
|
 |
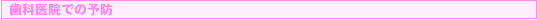 |
 |
歯周病のなりはじめは、痛みがないためみつけにくいものです。6ヶ月〜1年に一度は定期健診を受けましょう。
その際、歯面の研磨や歯石除去、不適合な冠の修正などの治療でプラーク形成を抑制することができます。 |
|
 |
|
|
 |